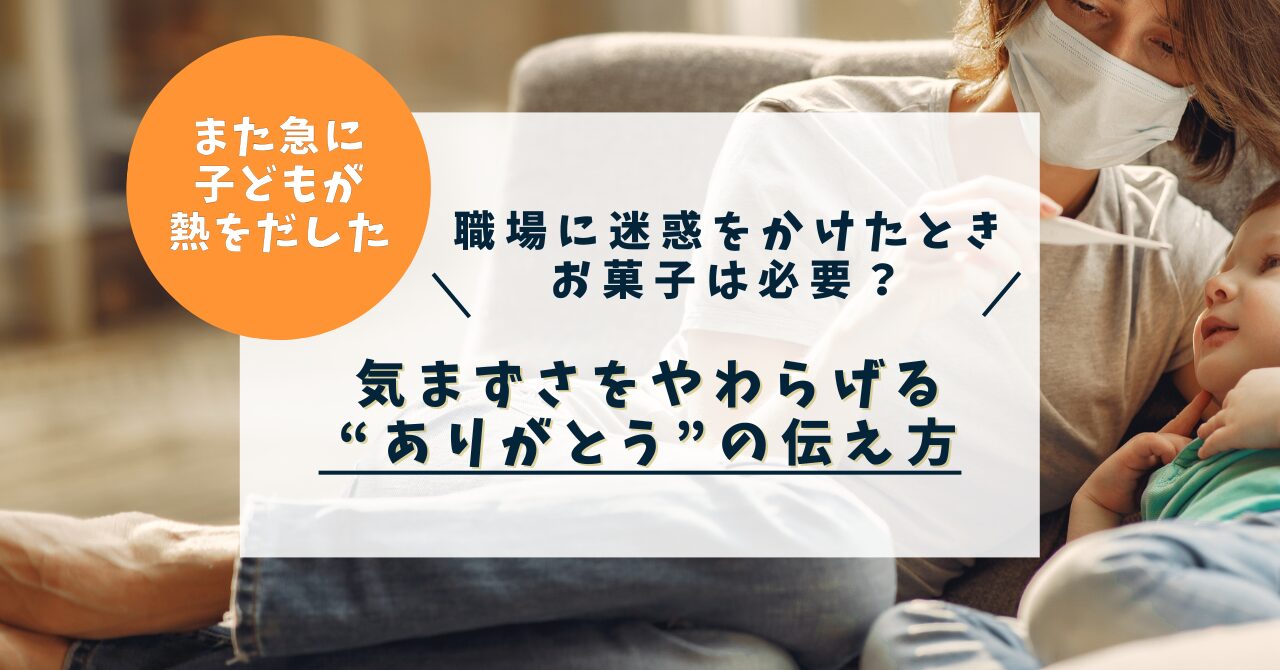【復職後が100倍ラクになる】復職前にやってよかった準備6選+やらずに後悔したこと
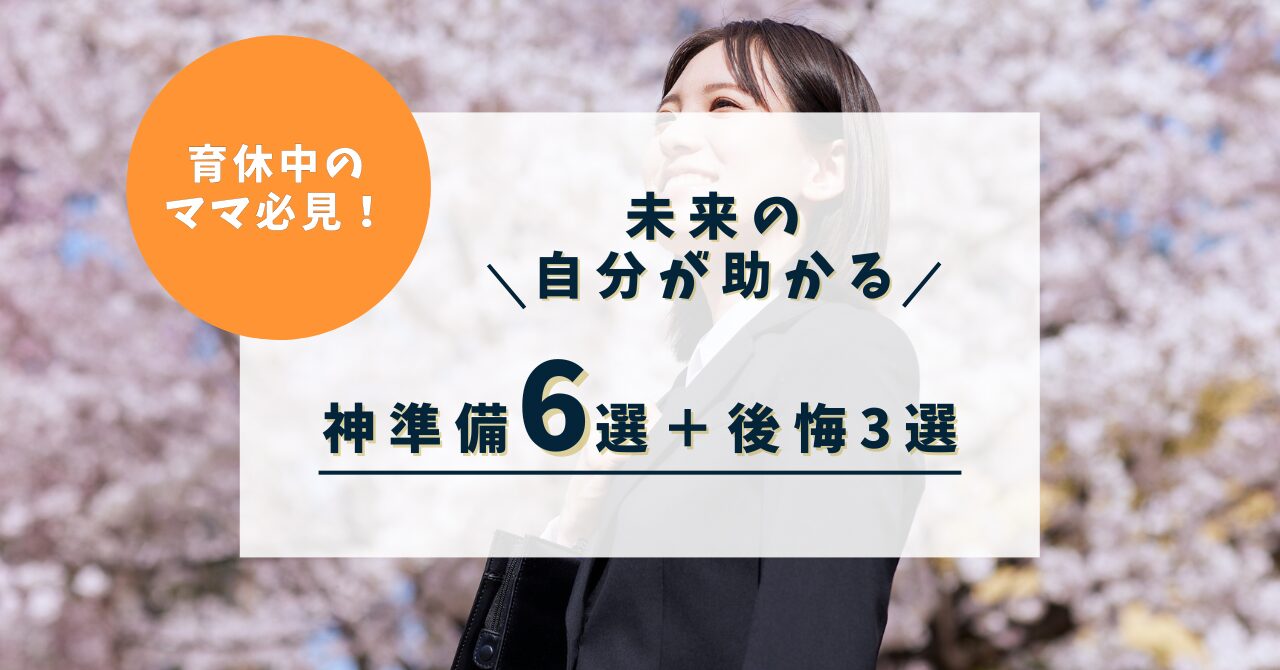
育休明け、久しぶりの社会復帰に不安を感じていませんか?「子どもが頻繁に体調を崩したら?」「仕事と育児・家事を両立できる?」「職場に迷惑をかけたらどうしよう…」そんなモヤモヤを抱えたまま復職の日を迎えるのは、とても不安ですよね。
実際、復職後は想像以上に大変です。子どもの体調不良で突然の欠勤、思うように進まない家事、家庭と仕事の板挟みに疲弊してしまうことも。私自身、復職1年目は毎月のように子どもの看病で休み、心身ともに追い詰められました。
そんな状況でも「これはやっておいて本当によかった!」と感じた準備がいくつかあります。逆に「これはやっておけばよかった…」と後悔したことも。この記事では、そんな私の実体験をもとに、復職前にやっておくべき準備を6つ+後悔ポイントを紹介します。
事前に準備しておくことで、復職後の生活はグッと楽になります。時間と心の余裕ができ、子どもにも優しく接することができるようになりますよ!
この記事を最後まで読めば、復職前にやっておくべきことが明確になり、不安が軽くなるはずです。ぜひチェックして、心の余裕を持って新しい一歩を踏み出してください。
復職前にやってよかったこと6選
1.【施設型病児保育の登録】

保育園1年目は、まさに試練の連続。ほぼ毎月風邪で休む、という現実に直面します。
そんな時の救世主が病児保育です。
病児保育とは、子どもが病気にかかっていて通常の保育園に通えない場合に、看護師や保育士が常駐する施設で一時的に預かってくれるサービスです。
発熱や風邪など、軽度の体調不良であれば利用できることが多く、保護者が仕事を休めないときの頼れる選択肢の一つになります。
多くの施設では、利用前に事前登録が必要です。予防接種歴や既往歴などの情報をあらかじめ提出しておくことで、スムーズに利用できます。育休中に登録しておくと安心です。

病児保育施設は自宅の近くにあるとは限りません。私もバスで通う施設を利用していました。大量の荷物と泣く我が子を抱えて乗るバスは、いつも以上に窮屈に感じ「これは何の修行だ…」と何度も心が折れました。登録施設を決める前に、実際に施設まで行ってみることをおすすめします。
施設型病児保育の登録方法
定員・定休日・預かり時間・追加料金・お昼やおやつ提供の有無を確認
病歴や予防接種歴などの必要事項を「利用登録票」に記入し、利用希望の施設に事前に提出します。利用登録票は役所や病児施設でもらうこともできます。
利用当日の提出を受け入れてくれる施設もありますが、限られるため育休中に登録は済ませておきましょう。
施設に電話をし、病児保育の事前登録をしたい旨を伝えれば、日程の調整をしてくれます。メールで事前登録が可能な施設も一部ありますが、施設の雰囲気や、経路を確認するためにも、一度足を運ぶことをおすすめします。
当日の利用について注意点
病児保育を利用するためには、下調べ・事前登録・心の準備がとても大切です。いざというときに慌てないためにも、余裕のある育休中に、実際に施設を訪れたり登録を済ませておきましょう。
2.【ファミリーサポートの登録】

ファミリーサポートとは市民相互の助け合い活動のことで、簡単にいうと近所のおばちゃん達に子育てを助けてもらえる仕組みです。
自治体が仲介してくれるので、知らない人にいきなりお願いするのではなく、事前に顔合わせや面談があり、信頼関係を築いたうえでサポートがスタートします。サポート内容は様々ですが、例えば下記のことをお願いできます。
- 保育園の送り迎えの代行
- 保護者が帰宅するまでの一時預かり
- 保護者の通院や用事の間の短時間預かり
各自治体により、利用時間や料金もまちまちですが、千葉市の例を記載します。
利用可能時間:6時~22時
利用料金:平日7時~19時 700円/時
※土日祝・年末年始・基本時間以外 900円/時
※1時間に満たない場合、1時間とみなします。
一部の自治体では、病児保育が可能な地域もあり、緊急時の選択肢が一つ増えるだけで心に余裕ができます。
ファミリーサポートの利用方法
子供を連れての面談が必要な場合もあります
初回はコーディネートに時間がかかるため、10日~2週間程度の余裕をもって依頼
依頼会員(子供同席)、アドバイザー、提供会員の3者で1時間程度依頼内容や子どもについて、ファミサポの制度について話し合いをします。
3.【パートナーとの徹底的な話し合い】
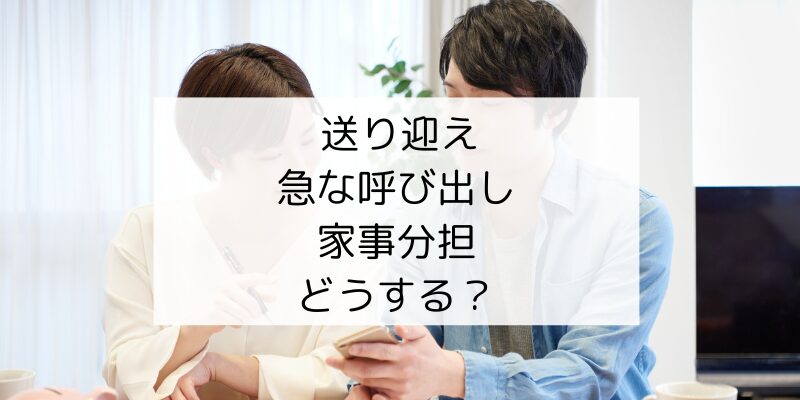
保育園の送り迎え、急な呼び出し対応、家事分担について、しっかり話し合っておきましょう。話合いをする上で、便利なアプリを紹介します。
【Yieto イエト 】 で家事を見て、話そう
Yieto (イエト)は夫婦が家事育児を一緒に乗り切るためのアプリです。夫vs妻ではなく、家事育児vs夫と妻、をサポートしてくれます。
家事分担を決めるうえで、現状の把握はとても重要です。このアプリを使えば最短で現状を可視化することができます。 その上で分担を決め、何度もトライ&エラーを繰り返しながら、理想の形に近づくことができます。対立ではなく、共闘を促してくれるアプリなので、冷静に話し合う土台を作ってくれるアプリです。

我が家は保育園への送りはパパ、お迎えはママが担当。緊急連絡はフレキシブルな働き方ができる、パパに入れてもらうようにしました。家事分担も最初に決めた通りにはいかず、生活しながら調整していきました。
4.【祖父母に協力要請】
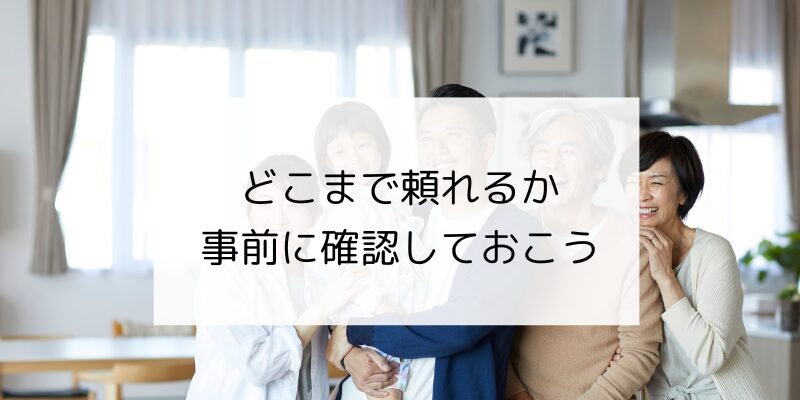
近くに住んでいる場合は、あらかじめ協力をお願いしておくと助けになります。

私の姉は両親に週2回お迎えから夕飯までお願いしていました。その間に溜まった仕事を片付けられ、精神的にも助けられていたそうです。ただし、子どもが病気の時は感染リスクを考慮し、お願いしないようにしていました。
5.【同僚・先輩ワーママからの情報収集】
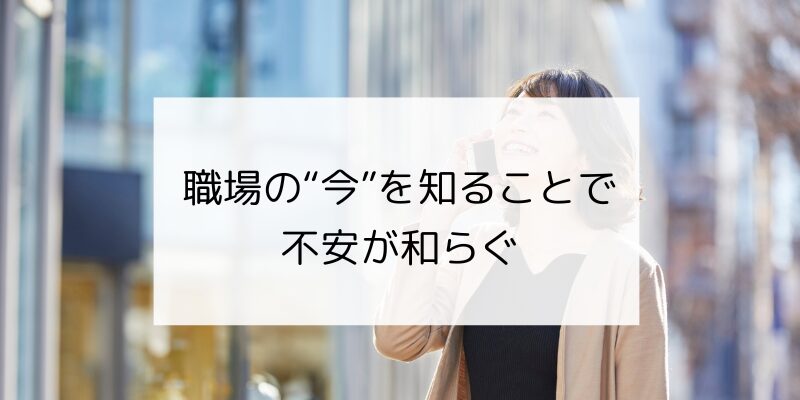
人事や業務フローの変更、先輩ワーママの働き方など、事前に知っておくと復職後のギャップが少なくなります。先に復職しているワーママの評判を聞いてみるのもよいでしょう。話の中から、気を付ける点・マネすべき点が見えてきます。

私は先輩ワーママとは連絡が取れなかったものの、友人から社内の変化や雰囲気を聞くことで、復職後のイメージをつかめました。
6.【リモートワークの可否確認&ネット環境の整備】
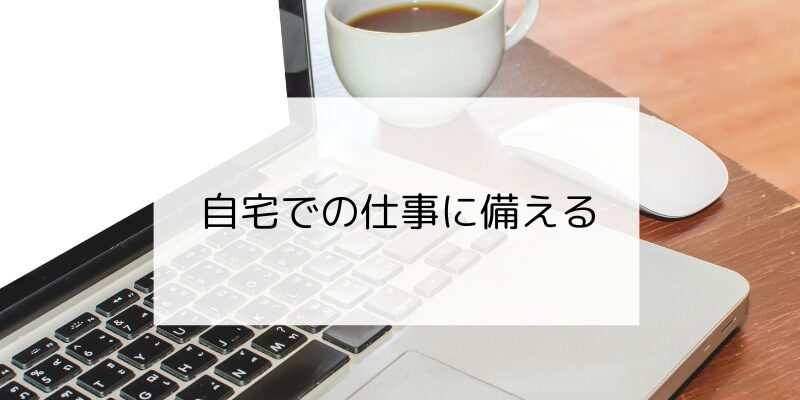
子どもが体調不良のとき、リモートで働けるかどうかを事前に確認しておくと安心です。欠勤せずに業務を続けられるため、職場に迷惑をかけているという罪悪感を減らせます。

我が家はマンション備え付けの回線を使用していましたが、リモートワーク時は動作が遅くストレスに。事前にネット環境を整備すればよかったと後悔しました。リモートワークがメインになる方は、ネット回線やルーターの見直しをしてもよいかもしれません。
子どもと過ごしながら仕事をするのは想像以上に大変です。回復期にある子どもが、親の隣で遊べるおもちゃを用意するのもよいでしょう。
復職前にやっておけばよかったこと3選
1.【訪問型の病児保育登録】
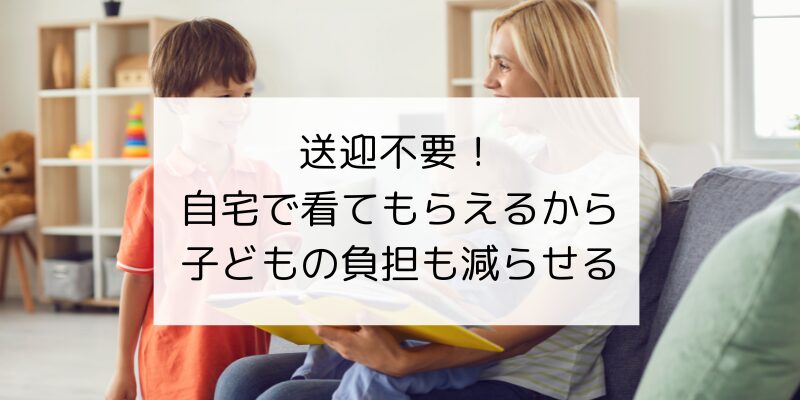
施設型は場所や定員も限られ、病児しか預かれないため、兄弟がいる場合、健康な兄弟の預け先がないなど、制約も多めです。
訪問型病児保育とは
看護師や保育士などの専門スタッフが自宅に来て、病気のお子さんを保育してくれるサービスです。施設に連れて行く必要がないため、移動の負担がなく、兄弟がいても家庭内で一緒に過ごせるのが大きなメリットです。
訪問型病児保育業者紹介
信頼の対応実績13万件を誇る認定NPO法人です。前日20時までの予約で派遣率95.2%(※2024年4月~2025年1月実績)を実現しています。
2004年の設立以来、重大事故ゼロを誇る認知度・実績ともにトップクラスです。
【対応エリア】
東京、千葉、神奈川、埼玉の一部地域に限られています。
【料金】
入会金、月会費、利用料、オプション費用、交通費が発生
全国で利用可能な、訪問型の病児保育サービスを提供しています。経験豊富なベビーシッターを、プロフィールから自分で選択することができます。登録料や月額費用は不要で、各シッターの時給に応じて予算に合わせた利用が可能です。
【対応エリア】全国
【料金】ベビーシッターによって異なる
病児保育、送迎、ご自宅での保育、留守番、外遊び、見守り、育児相談、出張先でのホテル内シッティング、加配(障がい児)保育、家事代行など、育児のお手伝いや家事のお手伝いに関わる事全般に対応してくれます。業界最安値水準の1時間2,200円(税抜)からお願いすることができ、他社では断られてしまったケースや、メニューにない場合も相談にのってもらえる、柔軟な対応が魅力です。
【対応エリア】全国
【料金】
2,200円/1時間(税抜)から
病児ケア追加料金+2,200円(税込)
感染対策+3,300円(税込)
病院受診+3,300円(税込)
入会金・年会費なし

長女の体調不良で3日休み、やっと復職……と思った矢先に今度は次女が発熱。結果、1週間以上連続で休むことに。訪問型を登録していれば、金銭的な負担は大きいけれど、復職1年目の信頼や職場への気まずさを考えると、利用する価値はあったなと感じました。
2.【生協などの宅配サービスやネットスーパーの申し込み】
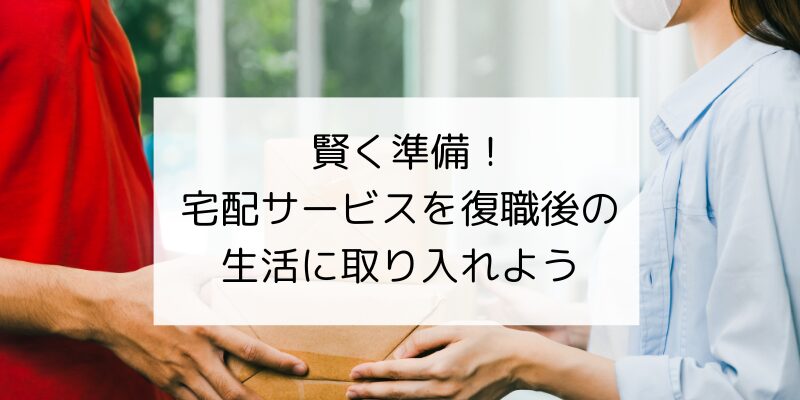
とにかく時間が足りない復職後、買い物やごはん作りの負担は大きなストレスになります。宅配サービスを利用する事で生活にゆとりが生まれます。宅配サービスにもたくさんの種類がありますが、主なものをいくつかご紹介します。
コープ・デリ/パルシステム
食材や日用品を毎週決まった曜日に、自宅まで届けてくれる宅配サービスです。どちらも、子育て世帯や共働き家庭に便利な仕組みが整っています。
- 離乳食向けの冷凍食材や、時短調理キットも充実
- 配達料は数百円(子育て割引あり)
- 国産・産直・無添加にこだわった安心食材
- 少ない調味料でも味が決まりやすい、時短ミールキットが人気
- 化学調味料不使用の商品も多く、素材重視の家庭向き
- 子育て割引で配達料無料になる地域もあり
どちらも、重い荷物を持たずに済むため、復職後の買い物負担をグッと減らせます。資料請求やお試しセットから始めるのもおすすめです。
つくりおき.jp
管理栄養士監修のもと、家庭的で栄養バランスのとれた「作り置きおかず」を週に1回まとめて届けてくれる宅配食事サービスです。冷蔵で届き、帰宅後5分で食卓に出せるので、忙しい共働き家庭や子育て中の家庭に人気があります。
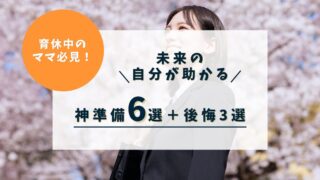
イオンネットスーパー
食品や日用品をオンラインで注文し、自宅まで届けてくれるサービスです。店舗と同じ商品をスマホやパソコンから選べるため、買い物に行く時間や手間を省けます。最短で当日配送も可能で、子育て中や仕事で忙しい家庭にとって心強い味方です。

私も当初は仕事後に子どもを連れてスーパーへ行っていましたが、寝るのが遅くなり、翌朝は起きられず負のループに。せっかくの休日も買い物で時間が削られ、子どもとの時間を十分に取れませんでした。
宅配サービスを使えば、子どもが寝た後にネットでポチっとするだけ。 必要なものが玄関に届くことで、心にも時間にも余裕ができます。
3. 【仕事復帰後の1日のスケジュールシミュレーション】
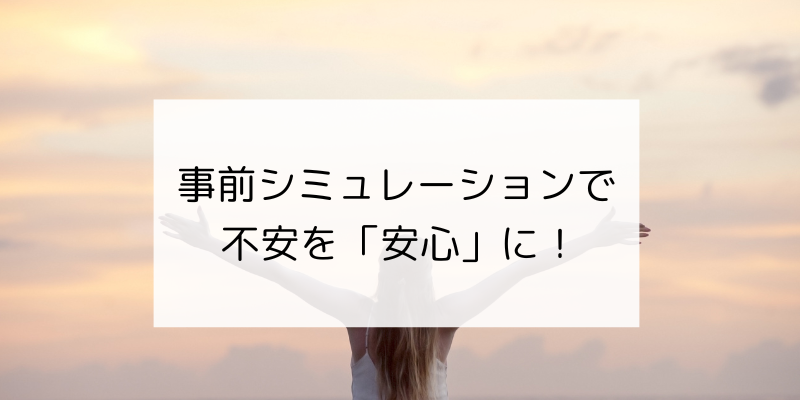
実際の生活を想定して一度動いてみると、準備の抜けや改善点に気づくことができたかもしれません。またパートナーとの家事分担を考えるうえでも、パートナーに当事者意識をもってもらえるよい機会になると思います。
【まとめ】“準備と話し合い”が復職成功のカギ!
復職前の不安は尽きませんが、少しの準備で気持ちと生活に余裕を持たせることができます。
復職前にやってよかったこと6選
- 【病児保育の登録】
事前に登録しておくことで、急な体調不良にも対応できる安心感がある - 【ファミリーサポートの登録】
いざというときの頼れる存在を確保。 - 【パートナーとの徹底的な話し合い】
家事・育児の役割分担をあらかじめすり合わせることで、いざこざを軽減できる。 - 【祖父母に協力要請】
協力可能な範囲を確認し、支援体制を整えておくと安心。 - 【同僚・先輩ワーママからの情報収集】
職場の“今”を知ることで復職の不安が軽減する。 - 【リモートワークの可否確認&ネット環境の整備】
自宅勤務の備えで、休まず仕事を継続でき罪悪感が軽減できる。
復職前にやっておけばよかったこと3選
- 【訪問型の病児保育登録】
施設型では預かれない状況にも、対応できる体制を整えておけばよかった。 - 【宅配食事サービスやネットスーパーの検討】
余裕がない時の選択肢を事前に探しておけば、もっと心が楽だった。 - 【仕事復帰後の1日のスケジュールシミュレーション】
実際の生活を想定して動いてみると、準備の抜けや改善点に気づけたかも。
この記事が、これから復職を迎えるワーママたちの参考になれば幸いです。あなたの毎日が少しでも楽になりますように。